宝くじ購入の豆知識!「宝くじの歴史について」
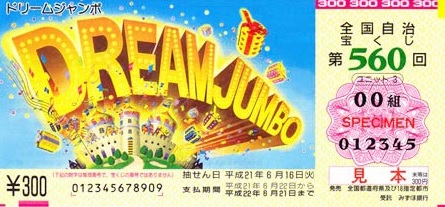
時代劇ドラマを鑑賞していると、
時々、「富くじ」 を取り上げた回が、あるのをご存じだろうか。
発祥は、江戸時代初期に、現在の大阪府である、摂津箕面の瀧安寺で、
正月に参詣した人々が、自分の名前を書いた木札を、箱の中に入れ、
1月7日に、寺僧が、キリで3回突いて当選者を選び、
福運のお守りを授けたのが、現代に繋がる、「宝くじ」 の起源と言われている。
最初は、お守りを渡すだけだったのが、
次第に金銭を渡すようになり、大流行したため、
一時、徳川幕府は、富くじを禁止した。
その一方、幕府は、寺社にだけは、
寺の修繕費用調達の方法として、富くじの発売を認めた。
これが、よく時代劇で取り上げられている風景である。
しかしその後、水野忠邦の推し進めた、「天保の改革」 で、
富くじは禁止され、明治に時代は変わっても、その傾向は続き、
「宝くじ」 として富くじが復活するのは、終戦直後の、
昭和20年10月のことである。
この、直前の昭和20年7月にも、軍事費を集める目的で、
富くじを復活させているが、抽選日を待たずして、
終戦となっているため、実質的な復活は、戦後といえる。
復活した理由は、戦後の荒廃期で、激しいインフレが予想されたため、
それを防ぐことが目的の、苦肉の策だった。
その後、経済復興と共に、宝くじの形態も変遷を遂げ、
1964東京五輪開催が決定した際は、開催までの5年間、
宝くじに、オリンピックマークが施された。
このように、宝くじの歴史はは、
国家的プロジェクトに協賛する形を取るようになってから、
人気も賞金も上がり、現在に至っている。

_44f7541b.gif)
